ほんの数週間前には桜色に煙っていた運河沿いの道も、これは桜の木だと知らされなければわからないほど、緑を濃くしていた。
真新しいランドセルを背負い駆け抜けてゆく子供も、その姿がすっかり板についたようにみえる。
桜の花びらと共に動きはじめた新しい旅立ちを振り返ることも既になくなっていた。
「……また出遅れちゃったかな」
菜穂子の口から自然に呟きが漏れる。
何かを始めようとすると、いつも一歩遅れをとってしまう。
今度もそうだ。
都会での暮らしも5年目になり、そろそろ心のほころびが気になりはじめていた。
それは社内での人間関係にも影響し、何となく転職を考え始めた矢先、会社が倒産した。
「まっ、仕方ないかぁ、いちど田舎にでも帰って……」
などと思案しているうちに、今度は会社の独身寮を明渡す期日になっていた。
他の住人はとうに引き払ってしまい、残っているのは菜穂子だけ。
ここでも出遅れていた。
引越しの準備を始めても、中々はかどらない。暮らした長さの分だけ溜まった思いを捨てきれないでいた。
菜穂子は息抜きの散歩に出た。
新緑の隙間を通り抜けた木漏れ日が心地よく包み込んでくる。
両手を頭上で組み、大きく伸びをした。
澱のように淀んでいた疲れが頭の先から抜けてゆく。
心底、気持ちよい。
そのとき背中に何かを感じた。
振り返ると、ひどく悲しげな表情をした10歳位の少女が、まばたきひとつしないで見つめている。
少女に微笑みかけようとした途端、新緑をざわめかせて吹いてきた春風が埃を巻き上げた。
一瞬、顔を伏せる。
再び視線を戻したとき、少女の姿は風と共に消えていた。
「変なの……」
また呟きがもれた。
そのまま運河沿いの道をしばらく歩くと、オープン・カフェがあった。
スチール製のテーブルの上で、木陰がゆれている。
老夫婦らしきカップルがひと組だけ、肩を寄せ合い、風にそよぐ若葉を眺めている。
その姿と耕介とが重なった。
耕介とは幼なじみだった。
そして、菜穂子が愛した唯一の男性。
いつからだろうか、気がついたときには、いつも耕介がそばにいた。
菜穂子が都会へ出てくるときは、耕介だけが反対した。
「行くなっ!菜穂子は俺のそばにいるのが1番似合ってる」
耕介らしい言い回しだった。
でも、都会暮らしへの憧れが菜穂子をせき立てた。
「だったら、耕介も一緒に来て」
「俺は行けない。この店がある」
そして、耕介は自宅の酒屋を継いだ。
婦人が老人に耳打ちをする。
老人の頬が緩み、つられて婦人の頬もそれ以上に緩む。
それは素敵にチャーミングな笑顔だった。
そのときになって、菜穂子は朝食を取っていないのに気づき、笑顔に引き寄せられるように店に入った。
メニューを見ると、モーニング・サービスは3種類で11時までとある。
店の時計で時刻を確認する。
まだ15分前。菜穂子はハム・エッグのついたセットをオーダーした。
若葉の香りを含んだ風が心地よく菜穂子の頬を撫ぜてゆく。
その先に、さっきの少女が立っていた。
菜穂子をじっと見つめている。
今度はじっくりと観察した。
髪はおかっぱ。
今にも折れそうなほど華奢な身体つき。
エンジ色のスカートから伸びた足はフラミンゴのそれのように細い。
何よりも、着ているキレイなピンク色のセーターとは対照的な暗く沈んだ目をしていた。
どこかで見たような……でも、思い出せない。
菜穂子は笑いかけてみた。
精一杯心地よい笑顔を作ったつもりだ。
少女の顔にも微笑が浮かんだ。
暗く沈んだ目にも明るさを見て取れる。
それは思いのほか人なつっこい顔だった。
……おまたせいたしました。
気の利いたトレイに乗ったモーニング・セットが運ばれてきた。
いつもの癖で、目をつぶり鼻から小さく息を吸い込む。
コーヒーの香りが身体の中に染みてゆく。
……あの子は?
視線を戻した先から、少女がエンジ色のスカートを翻して走り去っていった。
菜穂子は部屋へ戻り本の整理に取りかかった。
思い切って雑誌の類は捨てることに決める。
その中から、重なり合ってアルバムが出てきた。
家から持ってきたことさえ忘れていた。
はじめからページをめくってみる。
生まれて間もないころの自分がいた。
幼稚園の入学式、運動会と続いている。そして小学校……えっ!
菜穂子は一枚の写真に息をのんだ。
それは父が撮ってくれたもの。自宅の前で耕介と手を繋いでいる自分が写っていた。
おかっぱ頭、ピンクのセーター、エンジ色のスカート……
さっきの少女がそこにいた。
……そんなっ!
驚きはやがて心細さに変わり、菜穂子はそのまま動けなかった。
どれくらいたってからだろう、携帯の呼び出し音が菜穂子を覚醒させた。
そっと耳にあてる。
「はい」
「もしもし、菜穂子?」
耕介の声だった。懐かしい。なぜか涙が溢れてきた。
「うん」
それだけ言うのが精一杯だった。
「元気でやってるか?菜穂子の姉さんから番号を聞いたんだ。気になることがあったから……」
「……」
「今日、菜穂子にそっくりな子を見たんだ。ほんと、そっくりだった。でも、凄く淋しそうな顔してて……そしたら、菜穂子のことが凄く気になりだして……」
「ねぇ、その子って、ピンクのセーターにエンジ色のスカート?」
「なんだぁ、菜穂子、こっちに帰ってきてるのかぁ」
「ううん、私はずっとこっちよ」
「あれぇ。おっかしいなぁ。俺が見たのは小学校のグランドだぜ」
「いつごろ?」
「ついさっき。地面に何か一生懸命書いてた。菜穂子、もう、こっちには帰って来ないのか?」
「ん?……う、うん……」
「俺、ずっと待ってっからさ。きっと帰ってこいよ」
「うん。帰ったらすぐ連絡するね」
カーテンを取り外した窓からは春風が入り込んでくる。
「ずいぶん出遅れちゃったなぁ。」
携帯をしまいながら、そんな言葉が口をついた。
開かれたアルバムのページが、春風に煽られてパラパラとまた元に戻っていった。
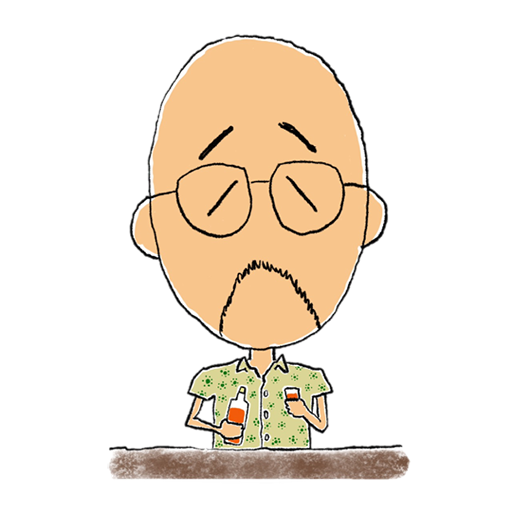
これはフィクションで、my Styleのお客様とは関係ありません。。。たぶん


コメント