深雪にとって化粧は鎧だった。
女を男の添え物としかみなさない職場で、男どもと伍して働くための武器である。
その威力とは言わないが、今は入社5年目にして6人の部下を持つ課長という地位にいた。
今の暮らしに不満はなかった。
ただ、自らを押さえつけていた緊張の糸の緩みからだろうか、近頃になり、女の盛りを仕事に費やそうとしている淋しさを感じ始めていた。
独身のまま、深雪は三十路を迎えようとしていた。
今朝も深雪は、戦場へ赴く戦士へと変身するため身なりを整える。
ファンデーションを塗りアイシャドウ、リップカラーと進むうちに、鏡の中では仕事ができ、おしゃれ心も忘れない女が創りあげられていく。
取れかけたマニキュアを塗り直しアクセサリーを付ける頃にはいつも通りのイメージができあがる。
これは深雪にとって、朝の出勤時には欠かせない儀式だった。
玄関を一歩出てからの自分の役割を、鏡に向かって確認するいつもの儀式。
しかし、今朝はそれに手間取っていた。
最後の仕上げのピアスが決まらないのだ。
理由はわかっていた。
深夜の電話である。
「もしもし、課長ですか」
まどろみかけていた頭の中を元気な声が駆け巡り、深雪は受話器を一瞬、耳から離した。
部下の山下だった。
「もしもし……」 山下の声が探るように変わる。
「寝てたんですか?」
「そう」
「すみません。起こしてしまって」
「いいわよ。で?今度は何をミスったの?」
「違います!酷いなぁ」
「じゃぁ、夜中の2時に、上司に電話をしてきた、それ以外の用件って?」
苛立ちを隠した分、事務的な冷たさで言ってしまった。
「すみません……」 山下の声が消え入るように途切れる。
「いいわよ、ところで何?」
「結婚しようと思うんです」 山下の声が弾んだ。
「おめでとう、良かったじゃない」
そのことで、どうして自分が起こされたのか判らないまま深雪は答えていた。
「違います。課長と結婚するんです」
「山下君」 深雪の口調はいつも社内で使うそれになっていた。
「こんな夜更けに君の冗談に付き合ってるほど余裕はないの」
「冗談なんかじゃありません」
「それなら、なお悪い。切るわよ」
「駄目!切らないで!」 山下の声が叫び声になった。
「酔ってる?」
「飲んでなんかいません。こんな大切なことを言うときに」
「わかったわ、聞いたげる。何があったか言ってみなさい」
暫く沈黙したあと山下が言った。
「部長から本社へ行くように言われました」
「えっ?!やったじゃない!おめでとう!君が認められたってことよ」
「課長のお陰です」
「私は何もしてないわ」
「部長から聞きました」
「ったく、部長は」 深雪は呟いた。
「でも、まだ返事はしてないんです」
「えっ?馬鹿ね!何やってんの、直ぐOKしなさい!」
「だから、課長の返事を待ってから」
「私とどんな関係が……えっ?……ちょっと待ちなさいよ」
深雪の中で切れ切れに散らばっていた糸がおぼろげながら紡ぎ合わされた。
「そう言うことね。でも、何故、私なの?」
「好きだからです」
「答えになってない」
「一番大切なことです」
「でも、すべてじゃない」
「僕にとっては深雪さんがすべてです」
課長から深雪さんに呼び名が変わっていた。
「君は私のことを何も知らないでしょ?」
「知ってます。入社してからずっと見つづけてきましたから」
「手を握ったこともない」
「キスしたことはあります」
「馬鹿言わないで!アレは酔った勢いでやったゲームに負けたからでしょ!」
「凄く濃厚でした」
「怒るわよ」
「もう怖くありません」
「いい加減にしなさいよ」
「深雪さんは無理してます。ずっと見ててわかりました。いつもバリバリ仕事して、何があってもくじけない。みんなに頼られて……。でも、ホントの深雪さんは違うでしょ?……もっと弱くて傷つきやすくて……」
山下は話し続けていた。そして、そのすべてが図星だった。
深雪が誰にも見せたことのない、脆くて傷つきやすい部分を山下は尽く言い当てた。
貼り付けていた鎧の重さが気になり始めていた深雪にとっては辛い言葉が続く。
明日、出社してから聞くと言って、深雪は一方的に電話を切ったのだった。
こんなこと、いくら考えても何も浮かぶはずはない。
それに、新しい企画が始動したばかりでそれどころではない。山下もそれぐらいは解っているだろう。
暫くは……
何も……
でも……
出社する時刻になった。
迷った挙句、深雪は、一番お気に入りのピアスをつけた。
ついぞ忘れていた熱い思いを蘇えらせてくれた若者のために。
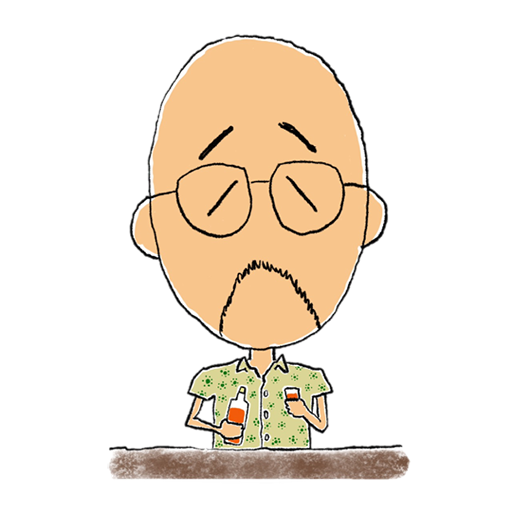
これはフィクションでmy Styleのお客様とは関係ありません。。。たぶん


コメント