思わずついたため息が欠伸に変わり、あまり眠っていないことに気付いた。
ほんの2時間ほど、それも浅い眠りを繰り返しただけだ。
「今からならまだ間に合うわね」
まだ明けきらない暗がりの中で時刻を確かめながらひとりごちる。
鉛のような身体を引きずりバス・ルームへゆき、熱いシャワーを当てた。
勢いよく飛び散る飛沫で幾重にも張りついたまどろみを、剥がすように洗い流す。
あとに現れたのは、やはりあの日の苦い思いだった。
*
父が逝って始めての命日。
わたしは仕事の関係で時間が取れず、昼前に参るという母たちより一足先に独りで父に逢いに行った。
早い時刻とあって墓地に人影は無かった。
入り口ですれ違った和服姿の女以外は。
彼女のあまりにも清楚でこの場には似合わない装いだけが記憶に残っていた。
今にして思えばあのとき気付くべきだったのだ。
入り口から十分ほど歩き父の墓前に立ったとき、それに気付いた。
墓は既に誰かの手によって清められていたのだ。
墓前は花で飾られ、供えられた物はすべて父の好物ばかり。
わたしの持参した物と寸分違わない。
小高い山の南に面した斜面に立ち並ぶ夥しい数の墓石の群れ。
それと同じ数だけの人生がその下に埋められているという思いが、わたしから考えることを奪い取っていた。
わたしの中のどの部分がそうさせたのか判らない。
気が付けば供えられた花と供物を傍らのごみ箱に投げ捨てていた。
酒瓶の割れる音が響き、追うように芳しさが辺りに広がる。
わたしは、既に洗い清められた墓石に幾度も水をかけ、血が滲むほど擦った。
冷え切った身体を暖めるように擦り続けた。
「バカ!」と言って父の胸に飛び込んで行きたい思いにかられた。
父はいつものように少しおどけながら受け止めてくれるだろうか。
まだ父の体温を感じられるほどわたしの記憶は暖かさを保っている。
その温もりがいっそう淋しさを募らせた。
夕方になり何も知らない母から、のん気な口調で墓を清めた礼を言われたときも、その淋しさは消えずにあった。
そして一年の時を重ねた今、わたしの中でひとつの思いが芽生えている。
わたしが父を愛したように彼女もまた父を愛し、そこにはいつもの父とは別の父がいたのだろう。
それはどんな父だったのだろう。
それを知りたくなっていた。
彼女の清楚な振る舞いに出会えたことで、今は彼女を違う目で見つめることができる。
同じ人を愛した女同士として話せそうな気がする。
さっ、早く行かなければ。今年は彼女より先に……
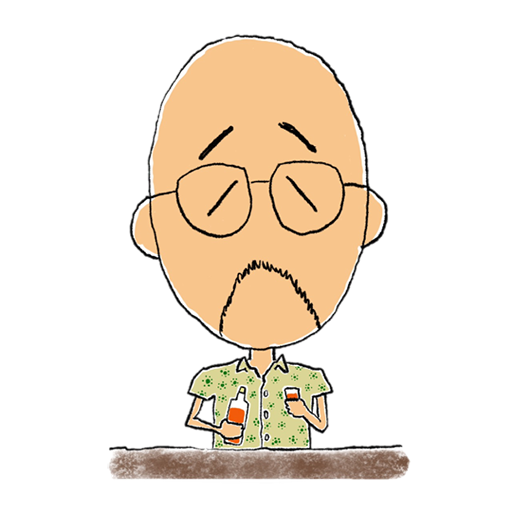
これはフィクションで、my Styleのお客様とは関係ありません。。。たぶん


コメント